いろんなところで子育てについて話す機会があったので、我が家の子育てと考え方を書いてみたいと思います
我が家に来たら、我が家のルール
息子が幼稚園に入るまではよく親子で遊びに来てもらってました
その時、我が家にきたら我が家のルールを守ってもらうべく、友達の子供も悪いことをすれば怒ります
注意や怒る事
・お菓子は座って食べる
・使わないおもちゃは片付ける
・物をもらったら「ありがとう」を言う
上記の事を普通だと思われる方と、幼稚園前の子にそんなことを言ってもわからないんだからと思われる方がいると思います
それでも我が家のルールです
守ってもらうべく注意や怒ったりします
お菓子は座って食べる
我が家はテーブルでなくこたつ机になります
小さい子には高さがあるので、我が子用には椅子がありました
友達はお母さんの膝に座ってましたが、それではちゃんと座ることが出来ないと思い牛乳パックで椅子を作りました

使い込まれた古い写真しか残ってませんでした
この他にてんとう虫柄もありました
作り方は牛乳パックの中に新聞を折りたたんだものを入れて、もう一つの牛乳パックで蓋をします

それを11個作って透明のテープでガチガチに固定します

この上に色画用紙を貼って、模様を切り貼りしてつけていました
「どれにすわる?」って聞くとお友達は我先に好きな柄を選んで座ってくれました
使わないおもちゃは片付ける

お友達のお家に行けば、自分の家と違うおもちゃがあり気になってあれもこれも出したくなります
それを次に行く前に声をかけて片付けるように言います
お友達がしなくても、我が子1人で片付けさせました
それをみてお友達のお母さんと一緒に片付けに参加してきます
子供は知らんぷりでも、お母さんが「○○くん(我が息子)がやってるからやりなさい」とさとしてくれます
物をもらったら「ありがとう」を言う
言って当たり前のことですが、恥ずかしかったり、言わない子もいます
お菓子を渡す時に手渡しで「ありがとう」を聞けるまで手を離しません
意地悪かと思われますが、もらって当たり前ではありません
言いたくなくて受け取らずにその場から離れる子もいます
でも、息子が食べてるのを見て食べたさに戻ってくるので「どうぞ」って声をかけると小さい声ですが「ありがとう」が聞けます
その時はちゃんと「どういたしまして」と笑顔でお菓子を渡します
遊ぶ時は全力で一緒に遊ぶ

公園で見守るだけでなく、一緒に参加します
それは大きくなっても同じで、小学生の鬼ごっこにも全力で参加
「ずるい」と言われようが手は抜きません
プールやスケートに行ってもそうです
トランプの神経衰弱やボードゲームでもそうです
勝たせて上げると図に乗るのと、負けて悔しいから次頑張るにつなげるためです
なので、ボードゲームは母ちゃん最強説です
出来ないとは言わない

私がハンドメイドをしているので子供からの無茶振りは日常茶飯事でした
これ作って、あれ作ってと言われますが出来ないとは言いません
時間のかかるものには「今はこれをしないといけないから、これした後ででいい?」と聞きます
どうしても欲しいものは「いいよ」と返事をくれます
後になれば子供は忘れている時はありますが、その時は言われるまでほっておきます
出来そうに無いものは、出来ないとの返事でなく「これはこうなっていて作るのにこれが必要だったり」と細かい説明や難しいことを説明すると「じゃあいいや」と折れてくれたりします
これは親の作戦勝ちですね
知らないとは言わない

子供から「これ何?」と聞かれたら、子供には難しくてもちゃんと説明します
どうしてもわからない時はスマホでこっそり見つからないように調べます
知らないと言ってしまうと知らないのを馬鹿にしてきたり、次を聞いてこなくなるのを避けるためです
大きくなってきたら「わからないから一緒に調べよか」とスマホで調べたのを「こうらしいよ〜、凄いね」って2人で勉強します
スマホだけ渡して「これ」って言ってしまったら、今度からはスマホを貸してってなると聞いてこなくなるからです
反対に今流行ってるのを「これ知ってる?」って聞かれたら、知ってる分は答えます
知らないのは知ったかぶりをせず「どんなん?」って聞きます
聞くとちゃんと説明してくれるので、子供から流行りはどんなのか聞くのが楽しいです
説明さすことによって、子供は理解し、頭で整理できてるかを知ることが出来ます
障害について話す

ちゃんと説明すれば、お友達にどう接すればいいか理解します
障害という言葉ではなく、人より困ることはあるから助けてあげるようには伝えています
人はそれぞれ違って個性なのだと言います
知り合いに耳が不自由なお友達がいます
小さい頃娘は「○○ちゃんの耳にキラキラのついたのつけてるの」って言ってきたことがありました
補聴器をデコっていたのがキラキラしていたみたいです
その時は「耳が聞こえないからつけているやつで、あれに触ると〇〇ちゃんは聞こえなくなるし困るから絶対に触らない。聞き取りにくいので口を大きく開けてゆっくり話してあげて」と伝えました
その後、同級生にも耳の不自由のお友達が来た時には、ちゃんと教えを守って話せたと何年も経ってますが耳が不自由のお友達の接し方がわかっているようです
愚痴は一緒に怒ってあげる

学校や友達関係で理不尽な事が起こります
家で子どもたちが愚痴った時は、一緒になって「最悪やなー」と合いの手をいれます
なんなら、それ以上にボロボロに言ってやります
そうすると子供は「そこまではないけどな」と言い過ぎなのを止めます
代弁することによって、スッキリするのと客観的に考えれるのかもしれません
なので、子どもたちは私を「毒吐きすぎ」「ディスりすぎ」と言います
反面教師で子供はそこまで言うことはありません
子どもたちに味方だと伝えます
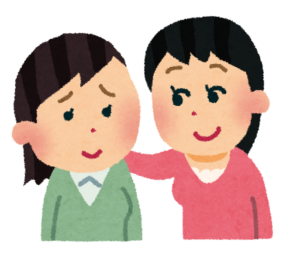
何かあって嫌なことがあれば「〇〇の味方だから、嫌なことがあればいいに言ってあげるから」と言っています
学校でも連絡帳に書こか?言いに行こか?と聞きます
子供はそれを聞くと安心するのか連絡帳に書かなくていいし、連絡しなくてもいいと言います
はたから見たらモンペアかもしれませんが、子どもたちを守れるのは親しかいないと思っています
子供が壊れるぐらいならモンペアと言われてもいい覚悟はとっくに出来ています
子供は親を見て勝手に育つ
実はよく見られているんです
教えなくても出来てて関心することがあります
人を助けてあげてると子供は「知ってる人?」って聞きますが、「知らないけど困っているから手伝ったんだよ」って事が小さい頃よくありました
そんな子供も困ってそうなおじいちゃん、おばあちゃんを手伝って帰ってきたと普通に話します
季節物はちゃんとする
日本の文化をちゃんと教えてあげたい
お正月・・・しめ縄を飾り、おせちを作っています
節分・・・豆まきをし、柊といわしの頭を玄関に飾り、恵方巻を作って食べます
ひなまつり・・・実家にあった7段の雛人形を飾ります
こどもの日・・・菖蒲湯にします
ハロウィン・・・飾り付けをし、ハロウィンらしいご飯をつくってい
冬至・・・お風呂にゆずを入れゆず湯にします。かぼちゃもたべます
クリスマス・・・飾り付けをし、サンタさんを待ちます
クリスマス用にご飯をしてパーティをします
最後に
子育て本が出ていますが一度も読んだことがありません
それぞれの個性で子育てに正解や不正解なんて、枠でしばることは出来ないと思っているからです
子育てで手がかかるのは人生のうちのほんのちょっとです
その時は辛いですが、後で印象に残りいい思い出にもなります
なので一緒にいれるうちは一緒に楽しもうと思っています
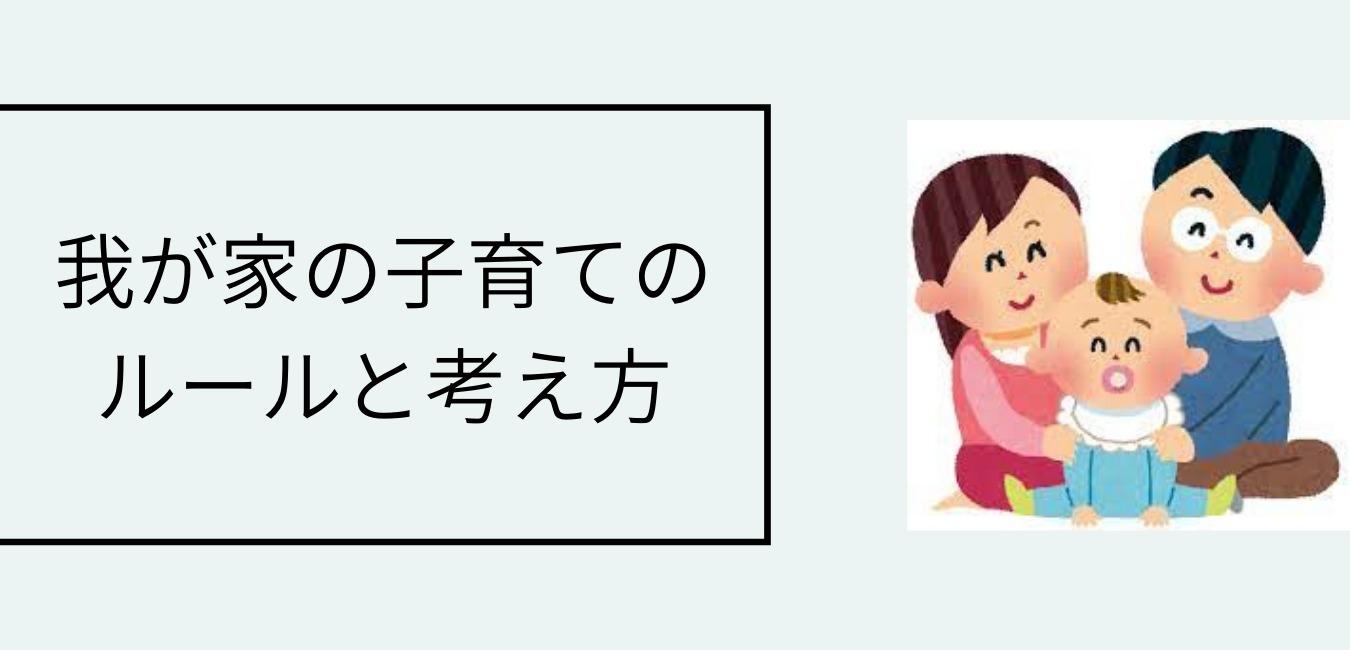
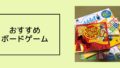


コメント